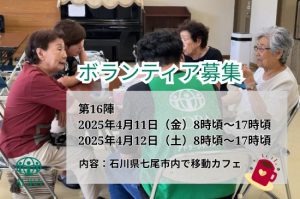能登半島地震から1年が過ぎ、被災地のニーズも変化してきている。
穴水町社会福祉協議会を含む町内6つの社会福祉法人では、中心地への買い物や移動に不便な2地区に、月に1回ずつお出かけ支援バスを運行している。新たに町東部の諸橋地区で実施することになり、昨年11月から車両や運転手の手配などの協力をしている。
「買い物に行くための足が無くてねぇ」
諸橋地区の住民がつぶやいた。そこで、社会福祉協議会の職員とお話を聴きに伺うことにした。
「この地区には独居の高齢者が多く、家から路線バスの停留所まで遠い人もいてね」
民生児童委員さんが話してくれた。この地区に他のバスが運行していないわけではないが、不便を感じている様子だった。
住民の話では、能登町のスーパーマーケットの移動販売もあるが、品揃えが限られているという。そのため、実施しているお出かけ支援バスでは、住民からの要望があれば、停留所まで遠い人を迎えに行き、ショッピングセンター以外に郵便局、ドラッグストア、コンビニなど、行きたい場所に立ち寄るなど、柔軟に対応している。さらに、住民にとって選択肢のある買い物を可能にしている。
利用する住民の中には、食品に加え、ペットボトルの水や肥料を購入する人が見られた。日々の活動の中で、震災以降水を購入して飲むようになったという話を耳にすることがある。ある仮設団地では、関心のある人同士で畑をつくり始めた。買い物の様子を通して、お出かけ支援バスが、住民の生活の質の向上にも寄与しているのではと感じた瞬間だった。

「周りの家が解体され、家から海を見渡せるようになってねぇ」
車内で住民から聞いたお話である。皮肉を交えて話す様子は、どこか寂しげだった。お出かけ支援バスは、住民の気もちの吐き出しの場としての役割も果たしているのだろう。
利用する住民の数だけで成果を図れるものばかりではない。私たちは引き続き被災者1人ひとりの声を大切にした支援を届けていきたい。
(文責:国内事業課 大澤 明浩)